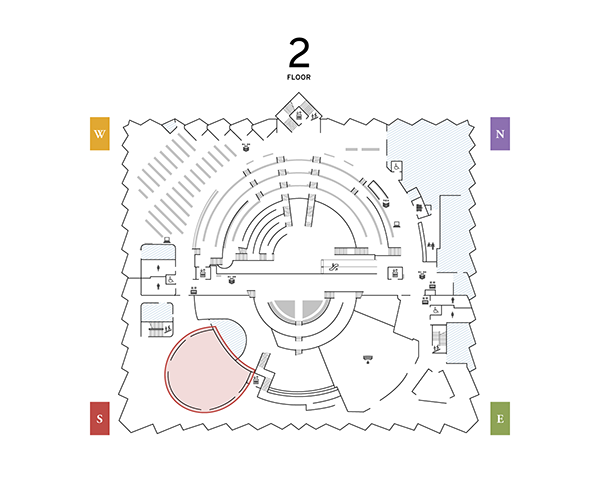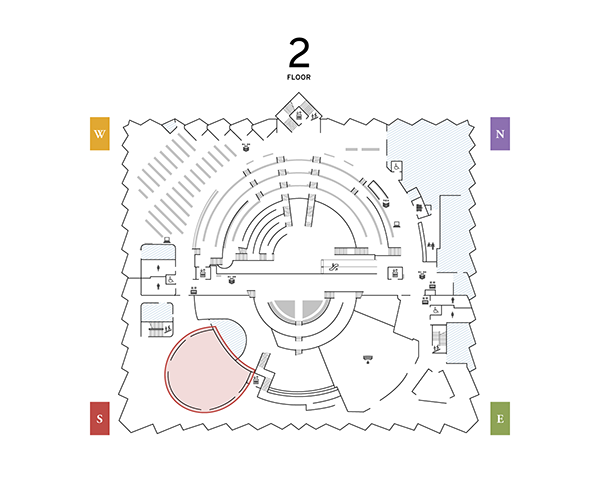【11月24日・30日・12月6日・14日】能登歴史講座「能登再興へのまなざし 歴史に根ざした地域づくり」
歴史を知ることは、単に過去の記憶をたどるだけではなく、現在を理解し、これからの歩みを考えるための大切な手がかりとなります。能登を深く研究している4名が、能登の成り立ちや人々の暮らし、文化をお話しします。能登の再興を考え、未来へのまなざしを持って向き合う時間をご提供します。
チラシはこちら(pdf 1,147 kb)
開催概要
|
内容
|
- 2025年11月24日(月・祝)
「大伴家持が見た古代能登の姿」
講師:森田喜久男(淑徳大学人文学部教授)
- 2025年11月30日(日)
「渤海使の見た能登・加賀」
講師:浜田久美子(大東文化大学文学部教授)
- 2025年12月6日(土)
「奥能登の古墳時代」
講師:伊藤雅文(石川考古学研究会副会長)
- 2025年12月14日(日)
「輪島にあった7世紀末の寺院」―稲舟窯跡出土瓦から考える-
講師:小嶋芳孝(金沢学院大学名誉教授、金沢大学客員教授、石川考古学研究会顧問)
|
| 時間 |
いずれも13時30分~15時00分 |
| 会場 |
- 研修室
- 研修室
- だんだん広場
- 研修室
|
| 定員 |
各140名 |
| 申込 |
事前申込制(先着順)
- 「大伴家持が見た古代能登の姿」への申込みはこちら
- 「渤海使の見た能登・加賀」への申込みはこちら
- 「奥能登の古墳時代」への申込みはこちら
- 「輪島にあった7世紀末の寺院―稲舟窯跡出土瓦から考える」への申込みはこちら
※イベント申込みについて
|
| 主催 |
石川考古学研究会
石川県立図書館 |
| 詳細 |
- 「大伴家持が見た古代能登の姿」
大伴家持は能登半島を巡行し、各地で和歌を詠みました。家持が能登を巡り抱いた思いは、やがて能登立国へとつながっていくのです。
- 「渤海使の見た能登・加賀」
奈良~平安時代には、日本海を越えて渤海国の使節が能登や加賀にやって来ました。どのような交流であったのか、渤海使の足跡をたどります。
- 「奥能登の古墳時代」
奥能登では、前方後円墳や大規模な古墳は確認されていませんが、これはこの地域が後進的であったからではありません。奥能登の特性を考えます。
- 「輪島にあった7世紀末の寺院―稲舟窯跡出土瓦から考える」
輪島市稲舟町の窯跡(七世紀末)出土の瓦は、近くで造営中の白鳳寺院に供給されたと推測できます。瓦作りの技術系譜から、能登最古級の寺院が輪島に建立された謎に迫ります。
|
講師
紹介 |
- 淑徳大学人文学部教授 森田 喜久男 氏
1964年生まれ。千葉大学大学院文学研究科終了後、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。駒澤大学大学院より、博士(歴史学)。
専門は日本古代史・神話学・博物館学。著書:『日本古代の王権と山野河海』(吉川弘文館2009年)、『能登・加賀立国と地域社会』(同成社2021年)
- 大東文化大学文学部教授 浜田 久美子 氏
1972年生まれ。法政大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。
専門は日本古代史。著書:『日本古代の外交儀礼と渤海』(同成社2011年)、『日本古代の外交と礼制』(吉川弘文館2022年)
- 石川考古学研究会副会長 伊藤 雅文 氏
1959年金沢市生まれ。1986年関西大学大学院文学研究科修了、博士(文学)。石川県教育委員会事務局、石川県埋蔵文化財センターで、遺跡の調査・保護に従事。
専門は日本考古学。著書:『古墳時代の王権と地域社会』(学生社2008年)
- 金沢学院大学名誉教授、石川考古学研究会顧問 小嶋 芳孝 氏
1949年金沢市生まれ。同志社大学文学部卒業後、石川県立郷土資料館、石川県埋蔵文化財センター、2005年より金沢学院大学教授、2019年より金沢大学客員教授。
専門は日本考古学・東北アジア考古学。著書:『古代環日本海地域の交流史』(同成社2023年)
|
2階:研修室